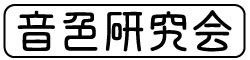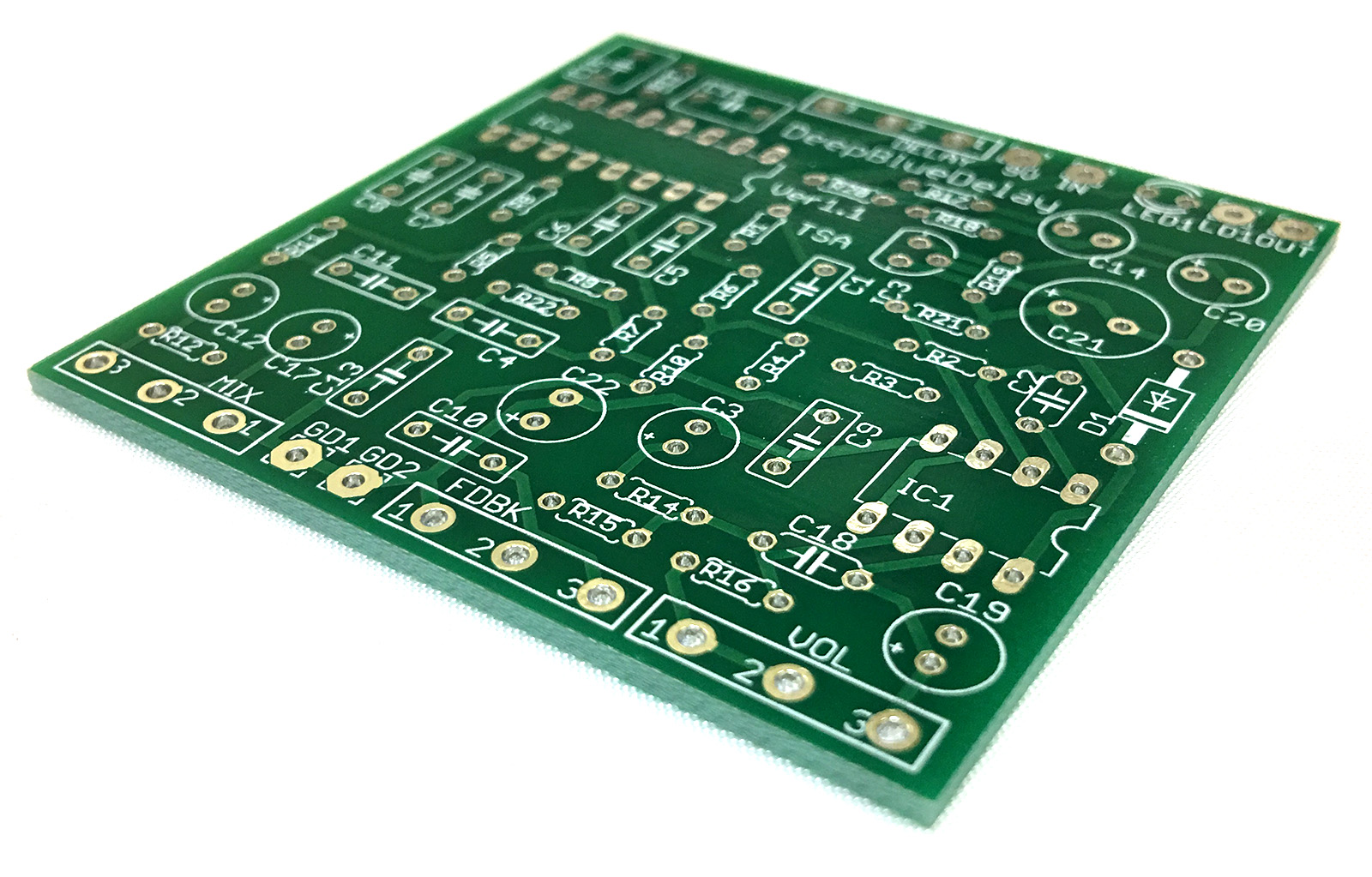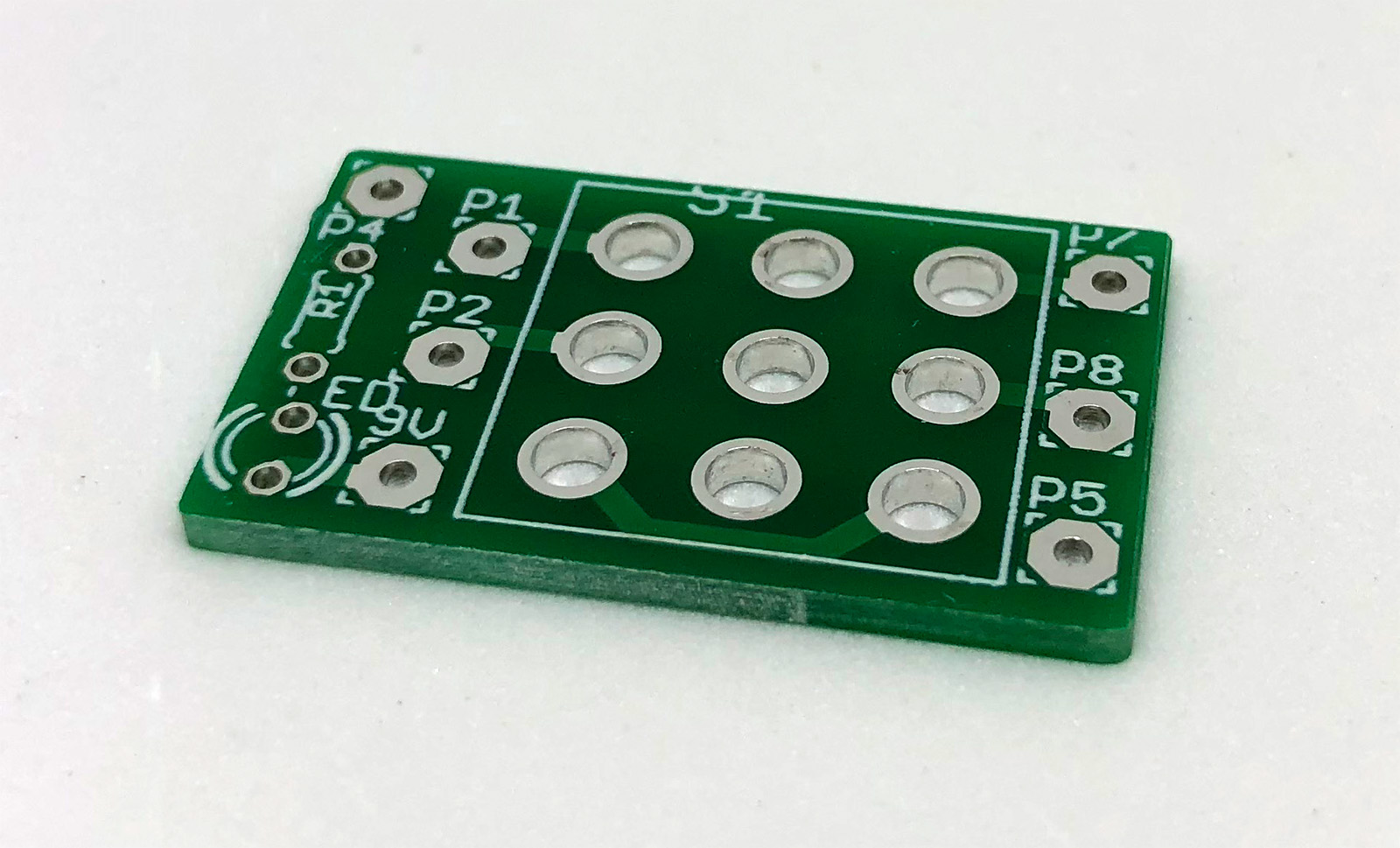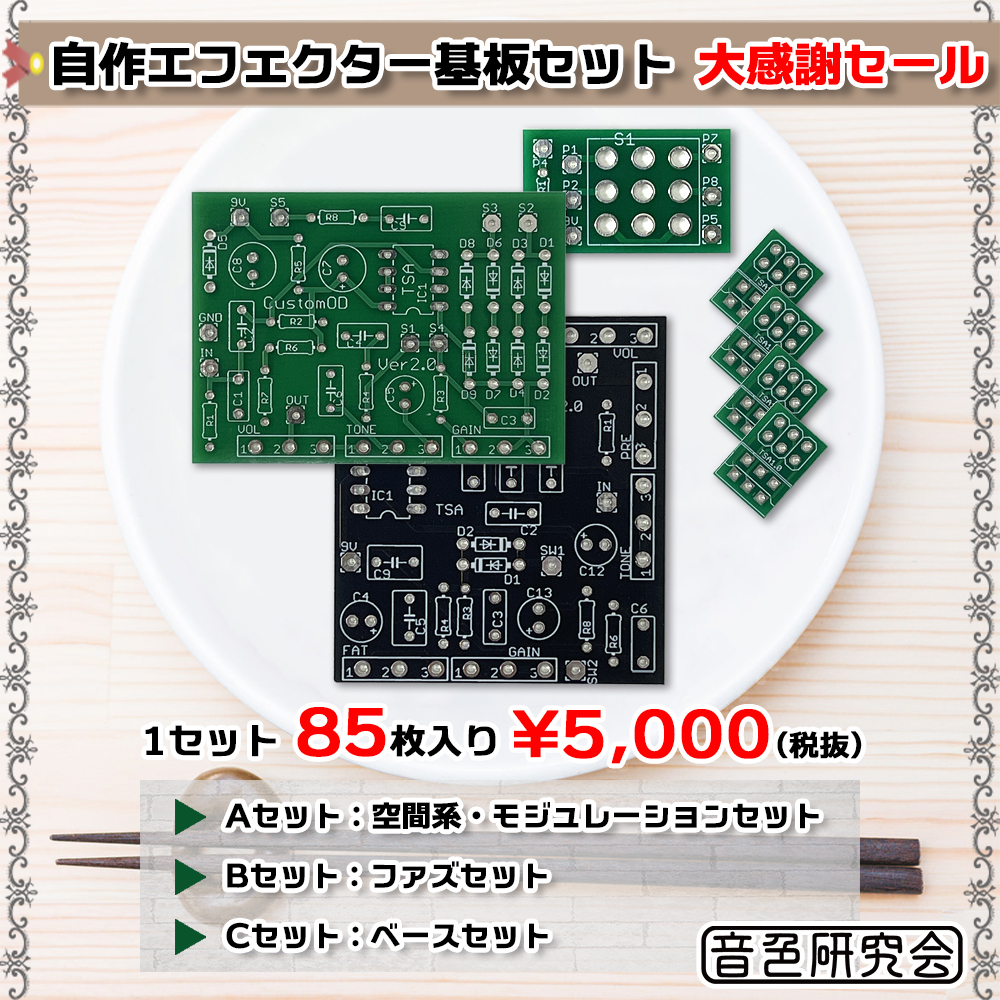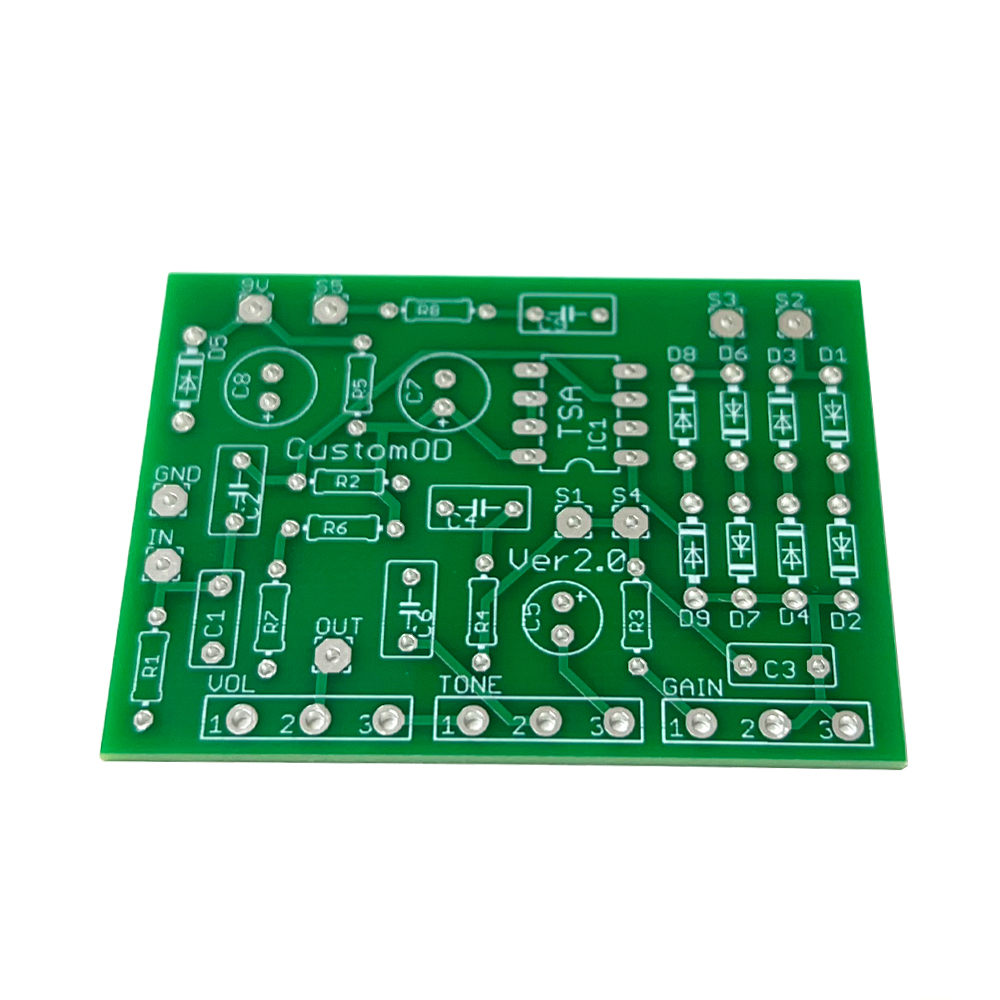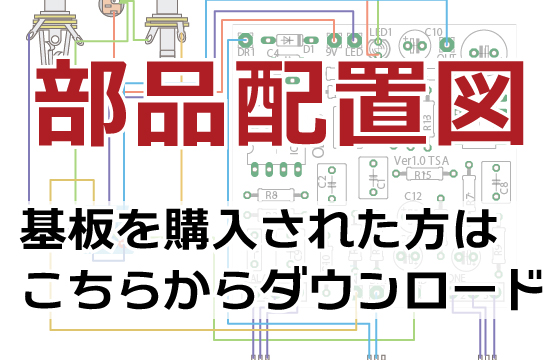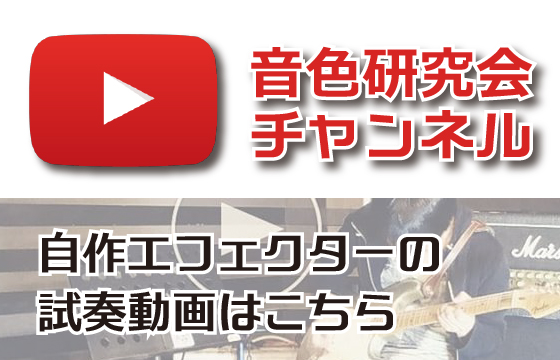ギターサークルでエフェクターを製作すると完成したのに音が鳴らないということがけっこうありました。
本気でトラブルシューティングするとなると専用機材が必要になってしまいますが、ほとんどの場合目視や簡易的な確認で対応できています。
音が鳴らない際にまずここを確認してくださいというものをいくつか紹介します。
①接触
過去に音が鳴らないエフェクターの原因のほとんどがこれでした。
まずはエフェクターケースの内面をビニールテープやクリアファイルを切ったものなど絶縁体であればなんでもいいので絶縁処理してください。
その後、蓋を開けた状態で音が鳴るか確認してください。
②配線や電子部品のリード線
自作初心者の方に多い例なのですが、配線の被覆を剥いてはんだ付けするときに剥いたリード線が長すぎる傾向にあります。
それと基板に電子部品をはんだ付けし、余分なリード線を切るときに余分を残しすぎている場合も多かったです。
これは他の部品などへの接触や短絡のリスクが増えてしまうことになります。
③部品の向きが間違っている
電子部品には向き(+と-)があるものがあります。
抵抗やフィルムコンデンサ、セラミックコンデンサに向きはありませんが、それ以外の電子部品には基本的に向きがあります。
④配線ミス
配線がたくさんあって慣れないうちは作っているうちにわかりにくくなってしまうと思います。
エフェクターの構造や仕組みなどを理解せずとも自作は可能ですが、「いまはんだ付けしている配線はバイパスのINだ」「これはエフェクターON時のOUTだ」くらいは理解しながら製作すると配線ミスも減るかなと思います。
実際にどのように配線するものなのか「実配線図」を紙に書いてみると理解しやすいのでお試しください。
⑤電子部品の不具合
古い絶版電子部品を使用すると多いです。
うちが試作する際には互換性のある汎用品で済ませてしまうこともありますが、気合が入っているときはがんばってとっくに生産終了している絶版品を使ったりしますが、これは10個中2~3個使えるものがあればOKという感覚でやっています。
ゲルマニウムダイオードなんかですとリード線を折り曲げる際にガラス部分が割れやすいので要注意です。
上記確認対応でほとんどの鳴らないエフェクターは対応できていました。
参考になれば幸いです。